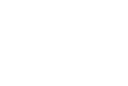Knowledge基礎知識
相続で揉めやすいケースと事前対策5つをわかりやすく解説
相続は、残された家族の生活を左右する大きな問題です。
相続人同士の関係が良好でも、財産の分け方をきっかけに揉めてしまうケースは少なくありません。
大切なのは、事前にできる備えをしておくことです。
今回は、相続トラブルを防ぐための基本的な対策をわかりやすく解説します。
相続に関するトラブルは増加傾向
「令和5年 司法統計年報(家事編)」によれば、相続に関する事件件数は近年増加傾向にあります。
たとえば「相続の放棄の申述の受理」の件数の推移は、以下の通りです。
| 年度(西暦) | 件数 |
| 令和元年(2019年) | 225,416件 |
| 令和2年(2020年) | 234,732件 |
| 令和3年(2021年) | 251,994件 |
| 令和4年(2022年) | 260,497件 |
| 令和5年(2023年) | 282,785件 |
遺言書関連の事件も、増えつつあります。
相続で揉めやすいケースとは
相続で揉めやすいケースは、以下の5つです。
- 遺言書がない
- 財産の大半が不動産
- 家族関係が複雑
- 元々家族仲が良くない
- 法律の知識がない
それぞれ確認していきましょう。
遺言書がない
遺言書がない場合、誰がどの財産をどのように相続するかを話し合いで決めなければなりません。
その際、相続人の意見が食い違うとトラブルに発展する可能性があります。
「自分が親の面倒を見てきたのに分け前が同じなのは納得できない」などの感情が、問題をこじらせる原因になります。
財産の大半が不動産
現金と違い、不動産は分けるのが難しい財産です。
売却して現金化するのか、誰かが相続する代わりに代償金を支払うのかなど、判断をめぐって対立するケースがあります。
また、不動産の評価額についても意見が分かれやすいのが現実です。
家族関係が複雑
再婚や内縁関係、認知された子どもがいる場合など、相続人の関係が複雑だと「誰がどの程度の権利を持つのか」がわかりにくくなります。
知らない相続人が後から登場して争いになるケースもあります。
元々家族仲が良くない
兄弟姉妹の関係が悪かったり、親との関係にわだかまりがあったりする場合は、相続をきっかけにトラブルが表面化しやすくなります。
相続財産の分け方そのものよりも、過去の不満や感情のもつれが争いの火種になるケースが少なくありません。
たとえば「不公平に扱われた」「疎遠だったのに同じ相続分なのは納得できない」といった気持ちが、冷静な話し合いを難しくする場合もあります。
法律の知識がない
相続は民法や税法など複数の法律が関わるため、専門的な知識がないと誤解や思い込みから争いが起きやすくなります。
「長男がすべて相続するべき」「面倒を見ていたから多くもらえるはず」といった思い込みで話がこじれてしまうケースもあります。
実際には法定相続分や遺留分といったルールがあるため、それを無視した主張は通らない場合がほとんどです。
事前にできる主な対策
事前にできる主な対策としては、以下の5つがあります。
- 遺言書を作成する
- 財産を「見える化」する
- 家族で話し合う機会を持つ
- 不動産の扱いを考えておく
- 専門家に相談する
それぞれ確認していきましょう。
遺言書を作成する
遺産の分け方を明確に示す遺言書があれば、相続人同士の話し合いが不要になる場合もあります。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、確実に内容を実現したい場合は、公正証書遺言を作成するのが安心です。
遺言書には以下のような内容を書きます。
- 誰に何の財産を渡すか(不動産、預金、株式など)
- 特定の相続人に多く渡す理由
- 遺言執行者の指定
ただし、遺留分を侵害するとトラブルの火種になるため、配慮が必要です。
財産を「見える化」する
残された家族が財産を把握できないと、相続手続きに時間がかかります。
預金、不動産、保険、借入金などを一覧にして、「財産目録」として残しましょう。
通帳や不動産の資料とセットで保管し、定期的に内容を更新します。
信頼できるひとに保管場所を伝えておくと、何かあった際もスムーズに事が進みます。
家族で話し合う機会を持つ
相続について話すことを避ける家庭も少なくありません。
しかし、家族の前できちんと「自分の考え」を共有しておくと、トラブルの予防につながります。
誰がどの財産を引き継ぐのか、何を大切にしているかを事前に伝えれば、亡くなった際に相続人が迷わず動けます。
事前に、相続に対する納得感を高めるのが重要です。
不動産の扱いを考えておく
不動産は相続トラブルの原因になりやすいため、事前にどうするかを検討すると安心です。
たとえば特定の相続人に引き継がせる場合は、その意図などを遺言書に明記してください。
分けにくい場合は、生前に売却し、現金にしておく方法もあります。
共有名義の場合は、そのリスク(「将来売却しにくい」「管理が面倒」など)も考慮して対策を考えるとよいでしょう。
専門家に相談する
弁護士などの専門家に事前に相談すると、相続に関する法的・税務的なリスクを減らせます。
「遺言書の内容が妥当かどうか」「遺留分への配慮ができているかどうか」「財産評価の正確性に問題はないか」など、個人で判断しにくい点もサポートしてもらえます。
相続が発生した後の手続きもスムーズです。
まとめ
相続は、財産の問題であると同時に、家族関係の問題でもあります。
相続人同士が争わないようにするためには、遺言書の作成や、財産の見える化、家族との対話など「今できる備え」を重ねるのが何より重要です。
トラブルの芽を摘むには、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。