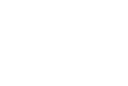Knowledge基礎知識
相続の不公平を防ぐ「遺留分」とは?制度の内容と注意点を解説
遺言書があると、被相続人(亡くなったひと)の意思に沿って財産が分けられます。
しかし極端に特定のひとだけに財産を与えたり、他の相続人にまったく残さなかったりすると、残された家族が困るケースもあります。
こうした不公平な状況を避けるために用意されているのが、「遺留分」という仕組みです。
今回は、遺留分の基本的な考え方と、請求の流れなどをわかりやすく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保障されている「最低限の相続分」です。
たとえ遺言書で「全財産を第三者に相続させる」と書かれていても、遺留分を侵害された相続人は、一定の割合まで取り戻せます。
遺留分が認められているのは、以下の法定相続人です。
- 配偶者(夫・妻)
- 子
- 直系尊属
兄弟姉妹は、相続人にはなれますが、遺留分がありません。
遺留分の割合
遺留分は、誰が相続人かによって、その割合は変わってきます。
以下、相続人の構成に応じた遺留分の割合を整理します。
全体の遺産に対する割合
遺留分は、相続財産全体に対して以下の割合で決まります。
- 配偶者・子がいる場合:法定相続分の1/2
- 相続人が直系尊属(親や祖父母)のみ:法定相続分の1/3
上記は、相続人全体で保障される遺留分の合計を示したものです。
そこからさらに、各相続人の法定相続分に応じて個別の遺留分額が決まります。
たとえば相続人が配偶者と子ども2人の場合、遺産全体に対する遺留分は1/2で、その1/2を配偶者・子2人の法定相続分に応じて分けることになります。
「遺留分の割合は、相続人の構成と法定相続分によって決まる」というのが重要なポイントです。
具体的な計算例
たとえば配偶者と子ども1人が相続人で、被相続人の遺産が4,000万円の場合、それぞれの遺留分は以下の通りです。
- 配偶者の法定相続分:2,000万円(遺産全体の1/2) → 遺留分1,000万円(法定相続分の1/2)
- 子どもの法定相続分:2,000万円(遺産全体の1/2) → 遺留分1,000万円(法定相続分の1/2)
遺言で配偶者にすべてを相続させる内容があったとしても、子どもは1,000万円まで請求できます。
別の例を考えます。
相続人が子ども2人(配偶者はすでに他界)で、遺産が6,000万円の場合、各相続人の遺留分は以下の通りです。
- 子どもAの法定相続分:3,000万円 → 遺留分1,500万円(法定相続分の1/2)
- 子どもBの法定相続分:3,000万円 → 遺留分1,500万円(法定相続分の1/2)
遺言で「全財産を子どもAに相続させる」と書かれていた場合でも、子どもBは1,500万円まで請求できます。
遺留分を取り戻すには
遺留分を取り戻すには、遺留分侵害額請求をする必要があります。
制度の概要や方法、期限などをそれぞれ確認していきましょう。
「遺留分侵害額請求」の制度
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年の民法改正により、現在は金銭での請求(遺留分侵害額請求)が基本となりました。
現物(不動産など)を取り戻すのではなく、金銭で補償してもらう仕組みです。
請求できる相手
遺留分を侵害する形で財産を受け取ったひと(受遺者や受贈者)に対して請求します。
たとえば、ある子だけが全財産を相続した場合、他の子がその相手に金銭請求を行います。
請求方法・流れ
請求方法・流れは、以下のステップです。
①相続内容の確認(財産目録の作成)
②遺留分の計算と請求額の算出
③内容証明郵便などで相手に請求通知
④話し合いがまとまらない場合は、調停・裁判
遺留分侵害額請求の方法は、法的に定められているわけではありません。
ただし証拠として残すため、内容証明郵便などで行うのが一般的です。
弁護士に相談して、書面作成や交渉を依頼するケースもあります。
請求の期限
遺留分侵害額請求には、以下の2つの期限があります。
- 相続があったことと、侵害されたことを知った日から1年以内
- 相続開始から10年以内
いずれか早いほうまでに請求しなければ、権利を失うため注意が必要です。
遺留分に関する注意点
遺留分に関する注意点は、以下の3つです。
- 遺言があっても無効ではない
- 生前贈与も対象になる
- 専門的な判断が必要なケースもある
それぞれ確認していきましょう。
遺言があっても無効ではない
遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、内容そのものが無効になるわけではありません。
ただし、他の相続人(たとえば配偶者や他の子ども)が遺留分の請求をすれば、長男はその分の金銭を支払う必要があります。
生前贈与も対象になる
被相続人が生前に一部のひとへ多額の財産を贈与していた場合も、その贈与分が遺留分の侵害に該当する可能性があります。
特に、死亡前1年以内の贈与や、特別に優遇された贈与は注意が必要です。
専門的な判断が必要なケースもある
遺留分侵害額を正しく請求するには、相続財産の評価や、過去の贈与の有無を正確に把握する必要があります。
不動産や株式などの評価が必要なケースでは、専門的な知識がないと正確な金額がわからないケースもあります。
また、証拠や書類の不備があると請求が認められない可能性もあるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するのが大切です。
まとめ
遺言があっても、その内容によっては遺留分を侵害している可能性があります。
請求期限があるため、内容に疑問がある場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談するのが重要です。
トラブルなく相続を進めるためにも、遺留分について正しく理解しましょう。