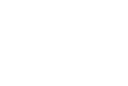Knowledge基礎知識
相続手続きの流れは?初めてでもわかる基本ステップを紹介
家族が亡くなったとき、避けて通れないのが相続手続きです。
慣れない言葉や書類に戸惑う方も多いかもしれませんが、手続きの流れを押さえておけば、焦らず対応できます。
今回は、相続が発生してから遺産分割・名義変更までの一連の流れをわかりやすくご紹介します。
相続開始からの基本的な流れ
相続の手続きは、一般的に以下のようなステップで進みます。
- 死亡届の提出
- 相続人の確定
- 相続財産の調査
- 相続方法の選択
- 遺産分割協議
- 名義変更・解約手続き
- 相続税の申告・納付
それぞれ確認していきましょう。
死亡届の提出
被相続人が亡くなった場合、まずは死亡届を役所に提出します。
戸籍法第86条第1項によれば、死亡届は、死亡の事実を知ってから7日以内に提出しなければなりません。
同時に火葬許可証も発行され、葬儀や火葬の手続きが進められます。
相続人の確定
次に、誰が相続人になるのかを調べます。
被相続人(死亡したひと)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)を収集してください。
相続人に漏れがあると、後の遺産分割協議が無効になる可能性があるため、慎重に進めるのが重要です。
相続財産の調査
相続財産には、預金・不動産・株式・自動車などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
この時点で財産の全体像を把握しておくと、相続方法をどうするかの判断に役立ちます。
相続財産の調査は、被相続人の所持品や郵便物などを手がかりにするのが基本です。
たとえば預貯金であれば、通帳や残高証明書で確認できます。
不動産の場合は、登記簿謄本、固定資産税通知書などで確認してください。
財産によっては時間がかかる場合もあるため、余裕をもって進めるのが重要です。
相続方法の選択
財産の内容がわかったら、次に「相続するかどうか」を選択します。
選択肢は以下の3つです。
| 相続方法 | 概要 | メリット | デメリット |
| 単純承認 | すべての財産と債務を引き継ぐ | 手続きに労力がかかりにくい | 借金が多い場合もすべて引き継ぐ必要がある |
| 相続放棄 | 一切の権利を放棄する | 借金などのマイナスの財産を一切引き継がずに済む | プラスの財産も一切受け取れない |
| 限定承認 | プラスの範囲内で債務を引き継ぐ | 借金があっても相続財産の範囲内での支払いでよい | 相続人全員の同意が必要であり、手続きも複雑 |
相続放棄、限定承認の場合は、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります(3か月以内に判断ができない場合は延長も可能)。
申述がない場合、原則として単純承認したとみなされます。
遺産分割協議
「遺産分割協議」とは、複数の相続人がいる場合に、遺産の分け方を話し合うことです。
話し合いの結果は、「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・押印します。
この書類があれば、不動産の名義変更や銀行口座の解約もスムーズに進みます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効になるため注意してください。
もし合意が取れない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
名義変更・解約手続き
協議がまとまったら、各種の名義変更を行います。
【不動産】
被相続人(亡くなったひと)の名義になっている不動産は、相続人名義に変更する登記(相続登記)が必要です。
手続きは、相続人の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
令和6年(2024年)4月から、相続登記は義務化されました。
正当な理由がないまま3年以内に手続きをしないと過料の対象になる可能性があるため注意してください。
【預貯金】
銀行などに預けていたお金は、相続手続きを行えば解約や払い戻しができます。
相続が発生すると、口座は一時的に凍結され、相続人の同意や必要書類の提出がないと動かせません。
金融機関によって必要書類やフォーマットが異なるため、事前の問い合わせが必要です。
【株式】
株式や投資信託などを保有している場合は、証券会社で名義変更が必要です。
非上場株式の場合は、発行元である企業とのやり取りが中心になります。
手続きをしないと、相続人は株式の取引を行えません。
証券会社によっては、遺産分割前の一部払出しができる制度もあります。
必要書類は財産の種類によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
相続開始から10か月以内に、税務署へ申告・納付しなければなりません。
期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることもあるため、早めの対応が重要です。
スムーズに手続きを進めるためのポイント
相続は感情や人間関係が関わる場面でもあるため、トラブルになりやすいのが現実です。
以下のような対策を意識して進めると、全体がスムーズになります。
- 戸籍や財産の情報は早めに集めておく
- 手続きの期限(3か月・10か月)をカレンダーで管理する
- 話し合いはできるだけ冷静に、書面に残す
- 不安な点は弁護士などの専門家に相談する
相続手続きは、計画的に進めましょう。
まとめ
相続手続きは、「相続人の確認」「財産調査」「分割協議」「名義変更」「税金対応」など、複数のステップで構成されています。
1つずつ丁寧に進めれば、相続トラブルを防ぎ、スムーズな承継につなげられます。
大切なひとの想いをきちんと引き継ぐためにも、余裕を持った準備をしてください。
不安があれば、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談するのがおすすめです。