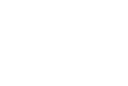Knowledge基礎知識
相続放棄できるケース・できないケースと注意点をわかりやすく解説
相続は、亡くなったひと(被相続人)の財産を引き継ぐ制度ですが、必ずしもすべてを受け入れなければならないわけではありません。
借金などのマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」を選べば、負担を避けられます。
ただし、相続放棄はすべての状況で認められるものではなく、一定の条件と制限があるため注意が必要です。
今回は、相続放棄できるケース・できないケースと注意点をわかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続権を完全に放棄し、「初めから相続人でなかったもの」とみなされる制度です。
相続放棄をすると、プラスの財産(預金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切受け取らず、相続人としての立場から外れます。
手続きは、家庭裁判所に申述して行います。
単に「相続しません」と宣言するだけでは法的に放棄したことにはならないため、注意が必要です。
相続放棄の期限
相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第915条)。
期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされ、放棄はできなくなります。
相続放棄ができるケース
相続放棄ができる(推奨される)ケースは、以下の4点です。
- 被相続人に多額の借金がある
- 遠縁の親族の相続人に突然なった
- 相続財産の内容が不明または不安定
- 遺産をめぐるトラブルに巻き込まれたくない
それぞれ確認していきましょう。
被相続人に多額の借金がある
最も典型的なケースは、相続財産のうち借金が大きく、プラスの財産を上回っている場合です。
たとえばローンや事業の負債、保証人としての債務などが該当します。
単に相続すると、相続人に金銭的負担がのしかかるため、相続放棄をして債務を一切引き継がないようにするのが一般的です。
遠縁の親族の相続人に突然なった
被相続人に配偶者や子がいなかった場合、兄弟や甥姪が相続人になるケースがあります。
面識のない親族の相続は、「関わりたくない」「財産状況がわからない」といった理由で放棄できます。
相続財産の内容が不明または不安定
相続財産に債務が含まれているか不明な場合や、権利関係が複雑な不動産、保証債務などが含まれている場合も、リスク回避のために放棄が検討されます。
不動産の管理が困難な場合などにも、放棄が選択されるケースがあります。
遺産をめぐるトラブルに巻き込まれたくない
遺産分割協議に関わる精神的・時間的負担を避ける目的で放棄するケースもあります。
相続は、お金が関係する分野でもあり、何かとトラブルが起こりがちです。
「親族間の争いに巻き込まれたくない」という理由も、放棄の正当な動機として受け入れられます。
相続放棄できないケース
相続放棄できないケースは、以下の通りです。
- 相続財産の一部を使ってしまった
- 3か月の申述期限を過ぎた
- 被相続人の財産を管理・処分していた
- 限定承認をした
それぞれ確認していきましょう。
相続財産の一部を使ってしまった
相続放棄をする前に、被相続人の相続財産の一部を使ってしまうと、原則として「単純承認(相続を承認した)」とみなされます。
たとえば「被相続人の死亡後、葬儀費用をまかなうためにその口座からお金を引き出して支払った」などの場合、相続財産の処分とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
3か月の申述期限を過ぎた
相続があったことを知った日から3か月を経過してしまった場合、原則として相続放棄はできません。
ただし財産の存在をまったく知らなかったなど、特別な事情がある場合は、申述が認められるケースもあります。
被相続人の財産を管理・処分していた
放棄を希望していても、亡くなったひとの財産を積極的に管理・利用していた場合、法律上「承認」とみなされる可能性があります。
たとえば、自宅を第三者に貸したり、車を売却していた場合などが該当します。
また、請求書の支払いなどをした場合も、「債務を受け継いだ」と判断されるため注意が必要です。
限定承認をした
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)も責任を負うという制度です。
民法では、相続の承認(単純承認または限定承認)を一度すると、その後に撤回や変更は原則として認められないとされています(民法第919条)。
限定承認を選ぶと、「やっぱり全部放棄したい」と思っても、家庭裁判所に相続放棄を申述できません。
基本的に、放棄の意思が固まっていないうちに申述するのは避けるべきです。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると、自分が相続しないことになりますが、その分の権利は次順位の相続人に移ります。
たとえば子が全員放棄すると、代わりに親や兄弟姉妹が相続人になるため、親族関係が複雑化する可能性がある点には注意してください。
また、相続放棄は口頭では成立せず、所定の書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。
申述書の書き方や添付書類に不備があると受理されないケースもあるため、慎重に準備を進めるのが重要です。
まとめ
相続放棄は、条件や注意点を理解しないまま進めると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
被相続人の財産には手を付けないようにし、相続人を確定させて話し合いを進めてください。
相続放棄を検討している場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談し、自分にとって最適な方法を見極めましょう。