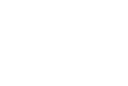Knowledge基礎知識
遺言書はどれを選ぶべき?3つの形式と書き方をわかりやすく解説
「自分の死後、財産をきちんと家族に渡したい」と思ったときに役立つのが、遺言書です。
遺言書を残せば、相続での争いやトラブルを防ぎ、希望どおりの形で財産を引き継いでもらえます。
今回は、遺言書の種類とその書き方について、わかりやすく解説します。
遺言書とは
遺言書とは、本人が亡くなった後に、財産の分け方などを伝えるための法的な文書です。
民法では、一定のルールに基づいて作成された遺言書には法的な効力があるとされています。
相続が発生した場合は、相続人同士の遺産分割協議を行い、その合意に基づいて遺産を分割するのが基本です。
ただし、遺言書があればその内容が原則として優先されます。
遺言書の主な3つの種類
遺言書の種類は、主に以下の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、すべてを本人が手書きで作成する遺言書です。
【特徴】
- 全文を自筆で書く(財産目録はパソコンでも可)
- 費用がかからない
- 日付、氏名、押印をする
- 法務局に預ければ紛失の心配がない
簡単に遺言書を作成したい場合に向いています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場に保管される遺言書です。
【特徴】
- 本人が公証人に内容を伝える
- 証人2人の立ち会いが必要
- 費用がかかるものの、検認が不要ですぐ使える
- 形式の不備によって無効になる心配がほとんど
より確実性を高めたい場合におすすめです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに作成できる遺言書です。
本人が作成した遺言を封筒に入れて、公証人と証人2人の前で提出します。
【特徴】
- 内容は自分で作成する(手書きでなくてもOK)
- 署名・押印をする
- 中身のチェックはされないため、形式ミスがあると無効になるリスクも
自筆証書遺言や公正証書遺言に比べると珍しい形式です。
それぞれの特徴を比較
自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言を比較した表は、以下の通りです。
| 種類 | 手軽さ | 費用 | 安全性 | 検認の有無 | 向いている人 |
| 自筆証書遺言 | ◎ | ◎ | △ | 必要(法務局保管時は不要) | 費用を抑えたい人、自分で準備したい人 |
| 公正証書遺言 | △ | △ | ◎ | 不要 | 内容に不安がある人、確実に遺言を残したい人 |
| 秘密証書遺言 | 〇 | △ | △ | 必要 | 内容を秘密にしたい人、専門家に頼りたくない人 |
それぞれの特徴を理解し、自分に合ったフォーマットを選んでください。
遺言書に書ける内容
遺言書に書ける内容はさまざまですが、たとえば以下のようなものがあります。
- 財産の分け方
- 遺贈・寄付
- 遺言執行者の指定
- 相続人の廃除や認知
それぞれ確認していきましょう。
財産の分け方
「誰に何を相続させるか」は遺言書の中心です。
不動産・預金・株式などについて、具体的な記載が必要です。
【具体例】
「〇〇銀行△△支店の普通預金口座(口座番号:1234567)を長女〇〇に相続させる」
遺贈・寄付
相続人以外の人や団体に財産を渡したい場合、「遺贈」として記載できます。
たとえば、内縁の配偶者、友人、福祉団体などが対象です。
【具体例】
「私の財産のうち、〇〇市△△町の土地および建物(登記簿番号:〇〇)を、内縁の妻△△に遺贈する」
遺言執行者の指定
遺言の内容を実行する人を「遺言執行者」といいます。
弁護士や信頼できる家族を指名すると、相続手続きがスムーズになります。
相続人の廃除や認知
特定の相続人を相続から外す「廃除」や、非嫡出子の「認知」も、遺言書で行えます。
いずれも遺言の内容を実現するには、遺言執行者の選任が必須です。
廃除の場合は、裁判所の手続きも必要です。
遺言書の作成例
以下、不動産と預金を相続させるための遺言書(自筆証書遺言)の作成例になります。
【作成例】
遺言書
1.私の所有する下記不動産を、長男山田太郎(昭和55年1月1日生)に相続させる。
所在地:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
地目:宅地
地積:120.00㎡
家屋:木造2階建(建物登記あり)
2.私の〇〇銀行△△支店の普通預金(口座番号:1234567)にある全残高を、長女山田花子(昭和58年1月1日生)に相続させる。
3.上記の遺言内容を実行するため、次の者を遺言執行者に指定する。
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
職業:弁護士
氏名:田中太郎
生年月日:昭和50年1月1日
以上、私の遺志を明確にするため本遺言書を自筆により作成し、署名・押印する。
令和6年4月11日
住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
山田 一郎(やまだ いちろう) ㊞
遺言書作成の注意点
遺言書作成の注意点は、以下の通りです。
- 書き方のルールを守る
- 遺留分への配慮をする
- 最新の内容を反映する
- 保管方法に注意する
それぞれ確認していきましょう。
書き方のルールを守る
特に自筆証書遺言は、形式に不備があると無効になる可能性があります。
署名・押印・日付の記載漏れ、財産の記述などに注意が必要です。
遺留分への配慮をする
相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
遺留分を無視した遺言を書いてしまうと、後からトラブルになることもあります。
最新の内容を反映する
遺言書を書いた後に状況が変わることもあります。
財産の内容や家族構成が変わったときなど、定期的に遺言を見直してください。
保管方法に注意する
自筆証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがあります。
令和2年(2020年)7月から始まった法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すれば、安心して保管できます。
まとめ
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶのが大切です。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら作成を進めると安心です。